はじめに:添加物の規制は国によって大きく異なる
私たちが毎日口にしている食品には、多くの食品添加物が含まれています。保存性を高めたり、色や味を調整したりと、食品を美味しく便利にする役割を担っています。しかしその一方で、海外では人体への悪影響が懸念され使用が禁止されているにも関わらず、日本では使用が認可されている添加物が数多く存在します。
この記事では、そうした「海外で禁止され、日本で認可されている食品添加物」を中心に、それぞれの添加物の役割、海外での禁止理由、日本での使用実態などを詳細に解説していきます。
1. 海外で禁止されているが、日本で使用されている主な食品添加物
以下では、実際に海外で禁止されているにも関わらず、日本国内ではいまだに使用が許可されている代表的な食品添加物を個別に紹介します。
亜硝酸ナトリウム(NaNO₂)
-
使用目的:発色剤・防腐剤(ハムやソーセージなどの加工肉に使用)
-
海外での扱い:EUやカナダなどでは厳格に使用量が制限されており、特に乳幼児食品には使用禁止。
-
問題点:体内でニトロソアミンという発がん性物質を生成する恐れあり。WHO(世界保健機関)は加工肉の摂取による発がんリスクを指摘している。
-
日本での現状:基準を満たす量であれば使用可。多くの市販加工肉に含まれる。
タール系色素(赤色102号・黄色4号・青色1号など)
-
使用目的:菓子、ジュース、漬物、アイスなどの着色
-
海外での扱い:ノルウェーやスウェーデンでは一部使用禁止。EUでは使用する場合「子どもの行動に影響を与える可能性がある」と表示義務あり。米国ではケネディjrが長官になり、使用禁止。
-
問題点:注意欠陥・多動性障害(ADHD)との関連が示唆されており、特に子どもの健康への懸念が強い。
-
日本での現状:食品衛生法で使用が認可されており、広く流通している。
BHA(ブチルヒドロキシアニソール)
-
使用目的:酸化防止剤(バター、ガム、インスタント食品など)
-
海外での扱い:イギリスでは使用禁止、アメリカでは動物実験に基づく注意喚起あり。
-
問題点:高濃度で摂取すると、動物実験において胃がんの発生率が上昇。
-
日本での現状:一定の使用基準内で使用が許可されている。
プロピオン酸カルシウム
-
使用目的:防カビ剤(パン、ケーキなどの焼き菓子)
-
海外での扱い:EUでは許可されているが、アレルギーや行動異常との関連を懸念する声もある。
-
問題点:子どもにおける行動障害や胃腸への刺激が報告されている。
-
日本での現状:防腐目的で広く使用されている。
臭素酸カリウム(KBrO₃)
-
使用目的:小麦粉改良剤(パンの膨らみを良くするため)
-
海外での扱い:EU、中国、カナダでは使用禁止。アメリカでも製パン業界の自主規制で使用は減少。
-
問題点:国際がん研究機関(IARC)では「ヒトに対しておそらく発がん性あり」と分類。
-
日本での現状:使用は認可されており、製パンメーカーによっては使用あり。ただし加熱で分解されるためリスクは低いという意見もある。
安息香酸ナトリウム(NaC₆H₅CO₂)
-
使用目的:保存料(清涼飲料水、ソース、漬物など)
-
海外での扱い:特定の濃度以上での使用は禁止(アメリカFDA)。EUでは基準超過で摘発事例あり。
-
問題点:ビタミンCと反応するとベンゼンという発がん性物質が生成される可能性あり。
-
日本での現状:使用基準を守れば認可されており、多くの飲料に含まれる。
2. なぜ日本では認可されているのか?
基準値の設定に差があるため
日本では、「一日許容摂取量(ADI)」に基づいて、添加物の使用量を厳密に制限しています。そのため、「微量であれば健康被害はない」と判断されている添加物については、使用が認められているのです。一方で、欧米諸国では「リスクが完全に排除できないものは予防的に使用を避ける」という「予防原則」の考えが強く、少しでも懸念がある添加物は使用禁止にする傾向があります。
食品業界と行政の関係性
日本では食品添加物の許認可において、業界側との連携や利便性を優先する傾向があります。製造効率や保存性の向上が優先され、消費者への明確なリスク表示が十分でないまま使用が続けられることも少なくありません。
表示義務の緩さ
日本の食品表示制度は、特定添加物のみの記載で済むことがあり、「一括表示」や「加工助剤」「キャリーオーバー」といった抜け道が存在します。そのため、実際に摂取している添加物の全容が消費者に伝わっていないのが現実です。
3. 消費者としてできる対策
食品表示をよく確認する
日頃から食品ラベルをよく確認する習慣を持つことが重要です。特に、亜硝酸Na、BHA、タール色素などの名称を見かけた場合には、別の商品を選ぶなどの判断ができます。
無添加・オーガニック食品を選ぶ
最近では「無添加」「オーガニック」「自然派」といった商品が増えています。多少価格は高くても、長期的な健康への投資と考えるとコストパフォーマンスは高いと言えるでしょう。
調理を手作りに切り替える
家庭での調理機会を増やすことで、加工食品に含まれる添加物の摂取を大幅に減らすことができます。自分の目で材料を確認できるという安心感もあります。
4. 今後の日本に求められる食品安全のあり方
科学的根拠に基づいたリスク評価は重要ですが、それと同時に「予防原則」の視点も取り入れるべきです。消費者にとってより安全な選択肢を提供し、リスクをゼロに近づける姿勢が、日本の食品行政には求められます。また、食品添加物のリスクに関する情報公開の強化や、分かりやすい表示制度の整備も急務です。
おわりに:知識があなたの健康を守る
食品添加物すべてが危険というわけではありません。しかし、海外では危険視されているものが日本で普通に使われているという事実は、知っておいて損はありません。正しい知識を持つことで、自分と家族の健康を守る選択ができるのです。今後は、表示を読み解き、より良い選択をしていく「消費者力」が試される時代だと言えるでしょう。
必要であれば、これらの添加物が含まれる商品例やより専門的な論文情報などもご提供できます。ご希望があればお知らせください。
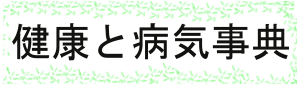
LEAVE A REPLY