若い人は入れ歯と無縁――そう思っていませんか?
実は20代・30代でも部分入れ歯や義歯を使用している人は少なくありません。歯の健康は年齢だけで決まるものではなく、生活習慣や疾患などさまざまな要因が関係しています。本記事では、若年層で入れ歯が増えている背景と、そこに潜むリスク、そして今日からできる予防法について、エビデンス(科学的根拠)に基づいて解説します。
若くても入れ歯を必要とする人が増えている理由とは?
日本補綴歯科学会や厚生労働省の調査によると、20代〜40代で部分義歯を使用している人は一定数存在します。特に30代後半から40代前半では、虫歯や歯周病の悪化により1本以上歯を失っているケースが多く、部分入れ歯やインプラントの使用者が年々増加傾向にあることが報告されています。
実際、2016年に発表された厚生労働省の「歯科疾患実態調査」によれば、35〜44歳の年齢層で1本以上の歯を失っている人の割合は約30%。そのうち義歯(入れ歯)を使用している人も一定数存在し、加齢以外の要因で歯を失うケースが無視できない現実となっています。
若年層で歯を失う主な原因
では、なぜ若いうちから歯を失ってしまうのでしょうか?以下が主な原因です。
・重度の虫歯(う蝕)
・歯周病(歯槽膿漏)
・不正咬合(歯並びの悪さ)や外傷
・喫煙や過度の飲酒
・糖尿病や骨粗しょう症などの全身疾患
・ストレスによる歯ぎしりや食いしばり
特に、歯周病は30代から急増する「静かなる病気」として知られており、初期段階では自覚症状がないため、気づかぬうちに進行し、気がつけば抜歯せざるを得ない状態になることも。
SNSやメディアでも注目される“若年入れ歯”の現実
近年では、TikTokやInstagramなどで20代のインフルエンサーが「部分入れ歯を入れてます」と公表するケースも出てきています。「見た目はきれいなのに、なぜ?」と思われるかもしれませんが、それだけ若年層にも“歯を失うリスク”が身近になっているという証拠でもあります。
また、入れ歯を使っていることを隠すのではなく、オープンに語ることで「同じ悩みを持つ人が安心できる」との声も増えており、SNS発の健康意識の変化にもつながっています。
若いうちに入れ歯をするとどうなる?デメリットと心理的影響
若い世代が入れ歯を使うことには以下のようなリスクや心理的な影響があります。
・発音しづらい・違和感がある
・外れやすいことへの不安
・見た目のコンプレックス
・食べ物が噛みにくくなる
・将来的にインプラントやブリッジへの移行が必要になる可能性
また、「周囲に知られたくない」「老けて見られそう」といった心理的負担も見逃せません。特に20代・30代の社会人では、職場でのコミュニケーションに影響を与えるケースもあります。
歯を失わないために今日からできる5つの対策
① 定期的な歯科検診(半年に1回が目安)
② 正しい歯磨き習慣(フロス・歯間ブラシも活用)
③ 糖質の取り過ぎを控える(虫歯菌のエサになる)
④ 禁煙・飲酒量の見直し(歯周病リスクが上がる)
⑤ ストレスマネジメント(歯ぎしり対策としてマウスピースも有効)
とくに、歯周病と全身疾患の関連は数多くの研究で明らかになっており、糖尿病や動脈硬化、心疾患などとの相関性も指摘されています。つまり、口腔ケアは全身の健康管理とも直結しているのです。
エビデンスでみる「若年入れ歯」と健康の関係
東京医科歯科大学の研究チームによる2019年の報告では、「若年期に歯を失った人は、将来的に生活習慣病やうつ病などのリスクが高まる可能性がある」としています。特に、20〜30代で奥歯を失った場合、その後の咀嚼能力の低下が栄養摂取や認知機能に影響することが示唆されています。
また、義歯の使用者と非使用者を比較した研究(Journal of Prosthetic Dentistry, 2021)では、若年層でも義歯によって生活の質(QOL)が改善した例がある一方で、適切なフィッティングやメンテナンスを怠ると健康リスクが高まることも指摘されています。
まとめ:入れ歯は“老化の象徴”ではない、むしろ予防が最重要
若くして入れ歯を使う人は少数派ではなくなりつつあります。その背景には、食生活の変化や慢性的なストレス、歯科受診の遅れなどが潜んでいます。
しかし大切なのは、「入れ歯にならないように、今から予防する」こと。定期的な検診と正しいセルフケア、そして生活習慣の見直しこそが、将来の健康な歯を守る最大のカギとなります。
今、自分の歯に自信がない方も、歯科医に相談することで大きな一歩を踏み出すことができます。入れ歯=年寄りという固定観念にとらわれず、早期予防・早期対策を心がけましょう。
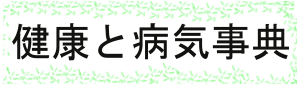
LEAVE A REPLY