国際がん研究機関(IARC: International Agency for Research on Cancer)は、世界保健機関(WHO)の一部門として、がんの原因となる物質や要因(発がん性)について科学的評価を行っています。IARCは発がん性のリスクを、科学的根拠に基づいて以下の5つのグループに分類しています。
-
グループ1:ヒトに対して発がん性がある(十分な証拠あり)
-
グループ2A:ヒトに対しておそらく発がん性がある(限られた証拠)
-
グループ2B:ヒトに対して発がん性がある可能性がある
-
グループ3:ヒトに対する発がん性について分類できない
-
グループ4:ヒトに対しておそらく発がん性がない(非常にまれ)
この中でも「グループ1」に分類された要因は、「ヒトに対して確実に発がん性がある」とされるもので、これがいわゆる「確実な癌の原因」とされます。IARCはこれまでに1200以上の物質や要因**を評価しており、グループ1に分類されているのは約130項目にのぼります(2024年時点)。以下では代表的なものをいくつかに分けて紹介し、そのメカニズムや社会的背景についても触れていきます。
1. 生活習慣関連の発がん性要因
喫煙(タバコの煙)
タバコの煙には70種類以上の発がん物質が含まれており、肺がん、咽頭がん、膀胱がん、肝臓がん、膵臓がんなど、様々ながんのリスクを高めます。受動喫煙も同様にグループ1に分類されています。
喫煙は、世界中で予防可能ながんの原因の中で最も大きな要因とされており、IARCの発表でも特に強調されています。
アルコール飲料
アルコールの摂取は、口腔がん、喉頭がん、食道がん、乳がん、肝がん、大腸がんなどのリスクを高めます。代謝過程で生成されるアセトアルデヒドがDNA損傷を引き起こすことが発がんのメカニズムとされています。
加工肉(ハム・ソーセージ・ベーコンなど)
2015年、IARCは加工肉をグループ1に分類しました。硝酸塩や亜硝酸塩などの保存料が、胃内で発がん性物質(ニトロソ化合物)を生成するためとされています。主に大腸がんとの関連が報告されています。
2. 感染症関連の発がん性要因
ヒトパピローマウイルス(HPV)
HPVの高リスク型(例:16型、18型)は、子宮頸がんの主因であり、男性においても咽頭がんや肛門がんとの関連が確認されています。HPVワクチンの接種により、がん予防が可能とされています。
B型・C型肝炎ウイルス(HBV・HCV)
いずれも慢性的な肝炎を引き起こし、最終的に肝硬変や肝臓がんへ進行する可能性があります。特に日本やアジア地域での肝がん患者の多くはこれらのウイルスに感染しています。
ヘリコバクター・ピロリ菌(H. pylori)
慢性的な胃炎から胃潰瘍、胃がんへと進行する可能性があります。除菌治療によって胃がんリスクを低下させることが可能です。
3. 職業的・環境的な発がん性要因
アスベスト(石綿)
主に肺がん、中皮腫の原因とされる鉱物繊維です。建築資材や断熱材などに広く使用されていましたが、現在では多くの国で使用が禁止されています。
ベンゼン
石油化学製品や溶剤として用いられるベンゼンは、白血病(特に急性骨髄性白血病)との関連があります。工場やガソリンスタンドでの曝露が問題視されています。
紫外線(UV)
太陽光に含まれる紫外線は皮膚がん(特に悪性黒色腫)を引き起こす原因です。日焼けマシンの使用もグループ1に分類されます。
4. 医療・医薬品関連の発がん性要因
放射線(電離放射線)
X線や放射性物質など、電離放射線はDNAを直接傷つける能力があり、白血病や甲状腺がんなどの原因になります。広島・長崎の被ばく者やチェルノブイリ原発事故の事例などが評価に利用されました。
ホルモン療法(例:エストロゲン+プロゲスチン)
特に閉経後の女性に用いられるホルモン補充療法(HRT)は、乳がんのリスク増加と関連があるとされ、使用の際にはリスクとベネフィットを慎重に考慮する必要があります。
5. 食品・飲料に関連する要因
アフラトキシン
カビ(アスペルギルス属)が生成する毒素で、主に穀物やナッツ類に発生します。強力な肝発がん性を持ち、特に開発途上国での肝臓がんと深く関わっています。
非加熱で提供される非常に高温の飲料
飲料自体が発がん性物質であるわけではなく、70℃以上の熱い飲み物が食道粘膜を損傷し、食道がんのリスクを高める可能性があります。特に南米や中国西部でのマテ茶・熱湯摂取習慣が調査の対象になりました。
まとめ:科学的根拠に基づく予防の重要性
IARCが「グループ1」として分類した要因は、いずれも広範な疫学調査や動物実験、分子生物学的研究を通じてその発がん性が「確実」と判断されたものです。これらを知り、日常生活の中でできる限り曝露を避けることは、がん予防において非常に重要です。
特に、以下のような対策が有効です:
-
タバコを吸わない・吸わせない
-
節度ある飲酒
-
加工肉の摂取量を控える
-
適切なワクチン接種(HPV、HBV)
-
ピロリ菌の検査と除菌
-
紫外線対策(帽子・日焼け止め)
-
職業上の化学物質への曝露回避
-
定期的な健康診断とスクリーニング
科学的な根拠に基づいた「がんの原因」を知ることで、個人の生活や社会全体での予防意識を高めることが可能になります。
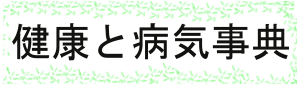
LEAVE A REPLY